先ず、県立図書館視聴覚室にて説明を受けました。
1図書館の概況(沿革・運営方針等) 黒岩 厚(次長)
・ 昭和54年8月 新築移転開館
・ 平成5年3月 電算システム導入
・ 平成21年度に開館創立80周年を迎える。
平成20年度主要事業
・ 県下66公共図書館の内、55館(770万冊)が参加して横断検索システムの構築。
・ 図書館未設置町村(29町村)支援。
・ 公共図書館情報ネットワークの構築 他
・ 平成19年度の蔵書冊数668千冊の内、約10%に当たる68.9千冊が郷土資料である。
また、開架冊数は110千冊(閉架550千冊)である。
2事業内容 干川 優(企画協力課主事)
パワーポイントにて特にレファレンス対応事例を詳細に説明していただいた。
企画展示について 関 藤夫(資料情報課長)
平成20年度は13回の企画展を予定
館内視察
・1階児童図書室と2階一般図書室、及び6階建の書庫の見学
※別途「県立長野図書館概要」参照
第2分科会 「公共図書館の経営と課題」
~図書館の創り方と運営・ハイブリット図書館を目指して~
司会者 山崎 良人(坂城町立図書館長)
発表者 宮下 明彦(長野県図書館協会事務局長)

1 発表の概要
県下、現在8自治体に図書館建設計画がある。他自治体でも図書館建設要望がる。 図書館建設への住民要望が強い
図書館建設には、億単位の資金が必要で、一回建てれば30年、40年と使い続ける。禍根を残さないためにも良い図書館を作らなくてはならない。
(1)図書館を創るポイント
・コンセプトづくり、特色作づくりには、住民、専門家・学識経験者(時代認識に基く専門的意見)の参画が必要。
・印刷媒体による資料に加えて、多様な電子媒体による情報も組み合わせて利用できるハイブリットな図書館を目指す。
・相互協力、相互貸借、情報ネットワークが不可欠。
(2)上田情報ライブラリー建設の経験から
・ 市民合意、コンセプトづくり(住民の声を反映させる)。①学習会、講演会、フォーラム等の開催による市民の理解・合意の形成。文化人の支援、図書館の将来を考える会。東京でのシンポジウム、ビジネス支援図書館推進協議会参加。市民公聴会、市長懇談会。
・ 資料・情報構築 コンセプトに基づく構築。雑誌、新聞(商用データベースも活用)、リーフレットの収集に力点。
・インターネット環境の整備。常設、貸出、持込のパソコン使用に適したスペースの確保。インターネット接続口40箇所。
(3) 今後の課題
・多種多様な情報提供がなされている中、公共図書館はそれを提供できる体制が不十分。
・図書館評価の新しい「ものさし」が必要。今の図書館サービスは、従来の貸出冊数、入館者数などだけでは評価できない(例:利用者の課題解決にどの程度役立ったか)。レファレンス統計の統一。講座・イベントの開催回数。目録・索引の整備状況、利用者満足度・・・。
・職員・スタッフの養成 ①専門性(レファレンス、情報サービス、読書案内、ブックトーク・・・)と②行政的能力(財政、人事、施設管理・・・)
・指定管理者制度 行政直営の図書館と指定管理者制度による図書館の並存時代。
2 討議(質疑応答)の内容
Q.指定管理者制度の図書館は期間が限られており、専門性を備えた職員が育たないのではないか。
A.サービスが向上しているので更新されていく。
Q.ハイブリット図書館は定着しているのか。
A.県下では、上田図情報ライブラリーだけ。ただ国の方針ではある。
Q行政資料の保存で、その資料の重要度を判断できる職員がいないがどうすればよいか。
参加者 スペースの問題はあるが、まずは保存すること。
~「知の消費」はもういいのではないか?~
助言者 なし
司会者 坪田秀彦(上田市立上田図書館)
発表者 平賀研也(伊那市立伊那図書館)
1. 発表の概要
・ 発表者の要望により、発表の前段として分科会参加者の皆さんの簡単な自己紹介から開始し、引き続いて平賀さんが自身の紹介も含め、伊那図書館館長としての新しい試みを発表された。
・ 平賀さんは大学卒業後20年間企業に勤務し6年前に伊那へ居住、昨年度から初代公募の図書館長として伊那図書館に勤務。「知の消費」ともいえそうな図書館をめぐる状況に、「誰のために」「何のために」を再定義し、いくつかの新しい図書館サービスを実施してきた。
- 「ブックパスポート」-子育てを楽しむー ブックスタートを「子育て支援」の共同
事業と再定義。子育てを楽しむツールとしてファーストブックを紹介、子どもとのふれあいも記録できる「第二の母子手帳」を作成配布。 - 図書館島の探検―図書館は楽しいー 子どもたちに図書館の第1印象を「わくわく、仲間と楽しむ場」にすることとし、休館日に宝探し・図書館ツアーを楽しみ、「情報の多さ」を体感。小学校の社会科見学・総合学習のプログラムとしても展開を広げている。
- 子どもの居場所―ことば・交流― 小学校・PTAと協議し、自由下校日を設定。新規分館図書館に寄り道し「異年齢交流の場に本とことばを」をめざしている。
- 図書館講座―もっと知ろう一緒につくろうー 図書館の実像を知り、一緒に考える機会として講座を開催。情報活用のスキルを学び、楽しみながら「すきなことを、すきなときに、すきなだけ地域の誰かのために」の機会提供につなげる。
2. 討議の概要(平賀さんの発表を聞きながら、自由に意見交換。時間が短く発表が主体)
- ブックパスポートについて
・アンケートをとったところ紹介の本を実際に読んでいる人は1~2人しかいなかった。ブックスタートについては疑問であり冊子を作っただけでは失敗であったという発表に、他館からは図書館の利用者の開拓も目的、ボランティアがその場で本を読んでやるのでやってよかったというお母さんの声も多いという反論があった。
・ブックスタートの意義としては、当たり前だと思ってやるのか、あのお母さんのためにやってみようという気持ちがあるのかが大事。 - 図書館島の探検について
・自分の子どもを図書館に連れて行ったら、いろんな本を探して喜んでいた。遊びとしてやって始まったことが、小学校3・4年生にも役立つことがわかった。子どもたちは本当に楽しんでいるので、小学校向けのプログラムという形でまとまった。
・このような企画をしている図書館は参加者の中ではない。 - 子どもの居場所としての図書館について
・小学校・PTAの了解をとってからの実施のため、下校時の寄り道について特に問題は起こっていない。本館に次いで市内では2番目に利用者が多い図書館になっている。 - 図書館講座について
・講座終了後は図書館ボランティアとして、各図書館で活動してもらっている。
・ボランティアは意外と図書館のことを知らない。きちんと話をし知らない人にしっかり図書館を知ってもらうことが大事。
3.まとめ
・ 自分に何ができるか、何がしたいか明確にすることにより、今まで図書館へ来ていた人だけではなく、すべての人のための図書館にしなくてはいけない。お客を増やすことが一番の課題。
利用者にとってより使いやすい資料提供のために」
~テイジー図書製作への取り組みを中心に~
司会者 鈴木 隆(長野市長野図書館)
発表者 増沢 雅彦(長野市長野図書館)

1 発表の概要
平成7年より「障害者ライブラリー」を開設し、養成講座を終了した録音図書・点訳ボランティアグループにより録音図書・点字図書の作成、貸出等のサービスを行っている。
・ 活動経過
平成17年度、県内デイジー図書作成グループからの情報収集を行い上田点字図書館からの図書製作依頼を受け、平成18年度よりデイジー図書製作を行うことを決定。
平成18年度テイジー編集者養成講座を開催し、講師を上田点字図書館より派遣。5名の編集者が誕生し、デイジー図書製作、テープ図書をデイジー図書に編集等進める。「DR-1」発売情報を受け、平成19年度購入し、講習会等を行ってきた。
2 討議の概要 「DR-1」
(1)利用者拡大及びPRについて
利用者の高齢化により、利用減少しているがどのようにして利用拡大をしているの か。
- 長野市においては視聴覚ライブライリーへの登録者82名中デイジー図書利用者 約15名。利用者及びボランティアの強い要望ではじまったため、特にPRはし ていない。
- 個人情報保護の関係で、民生委員を通じての拡充。
- 見えないと情報が入ってこないため、逆にデイジー図書を送りつける等積極的に PRするのはどうか。
(2)著作権問題、デジタル化等のデイジー図書作成にかかわる問題について
- テープ(アナログ)からの取り込みについても許諾が必要となるため、はがき等で許諾をもらっている。
- 日本図書館協会及び日本文芸協会等の一括許諾名簿に掲載のものは個々に許諾を
を受ける必要がなく活用できる。 - 利用者としては、中には著作権の許諾がとれないものがあるとのことだが、多くのものを聞きたいので、ぜひ著作権問題をクリアしてほしい。
- 作成にあたって、マイクの扱い方、口からの角度等録音技術で明瞭な録音をし
てほしい。
(3)プライベートサービスについて
- 図書館の蔵書の中からではなく、利用者としては読んでほしいものをニーズに合わせて作ってほしい。
- 日本点字図書館は、有料だが都民であれば作成している。
3 まとめ
県内各地域のボランティア団体で、実際デイジー図書作成に携わっている方々の参加 が多く、より実践的な意見交換ができたのと同時に、利用者の率直な意見も参考になった。
利用者拡大の方策、著作権問題等課題は多いが、利用者のニーズに合わせて図書館とボランティアと協力し録音資料のデジタル化を進めていく必要がある。
~司書教諭としての第一歩~
司会者 小林 康宏 (芦原中学校)
発表者 大沼田眞理子(並柳小学校)
林 尚江 (岡谷小学校)
大林美智代 (美篶小学校)
吉田 真弓 (篠ノ井西小学校)
北村 直子 (戸倉小学校)
小林 康宏 (芦原中学校)
山口 裕子 (上田東小学校)
堀内 京子(若槻小学校)
岡田真美子 (平岡小学校)
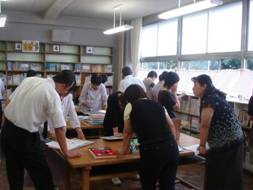
1 発表の概要
司書教諭としての実践事例を演習形式で発表
《小学校 低学年》
国語科の単元学習に図鑑を使った実践事例。1年「じどう車くらべ」2年「サンゴの海の生きものたち」で、本文に出てきた車や生きものを図鑑の索引を使って調べる。索引は巻末にあること、索引の順番は五十音であること、数字はページを表して太い字は主に出ているページであるなどの利用指導をした。低学年から系統的に行いたい。
《小学校 中学年》
4年生で使い始める地図帳の指導の実践例。地図帳の使い方は、座席の表し方と似ていると説明するとわかりやすい。まず、調べたい場所を索引で探し、ページを特定する。縦の列と横の行で更に絞り込んでいくことを指導し、実際にいくつか問題を用意して調べさせる。ゲームなど取り入れ、遊ぶこともできる。
《小学校 高学年》
百科事典・年鑑を使った「環境を守る」調べ学習の実践例。まず、テーマからイメージをふくらめて小テーマを作る。百科事典の索引で、調べる言葉の出ている巻とページをカードに書き出す。カードを元に小テーマに合わせて調べていく。同時に年鑑の使い方の指導をする。複数の資料を工夫してまとめていく。
《中学校》
パスファインダーとは、調べたいと思うことがらについて役立つ資料を、わかりやすく紹介した一枚チラシである。自分で設定したテーマに関してのパスファインダーを生徒に作らせる授業では、本のタイトル、目次、調べたいことに関係する言葉を参考に本を探していくことを指導する。十進分類法を知っておく必要がある。
《あれこれ》
本の展示の工夫、絵皿で作る絵本、簡単な絵本作りなどの本と子どもをつなぐ楽しい実践事例の紹介。
2 質疑
○ 中学校では、どのように司書教諭が授業に入ったらよいか。
・ 自分の受け持つ教科の時間で扱っていく。
・ 協力してくれる先生方でネットワークを増やしていく。
・ 朝読書が縮小されてきた学校もあるが、職員の理解を得ていくことが大切である。
3 世話役の先生より
○ ネットワークを張っていくことは大切である。また、管理職の先生方の理解も大きい。研修会も大切だが、実践して伝えていくのが、司書教諭の仕事である。